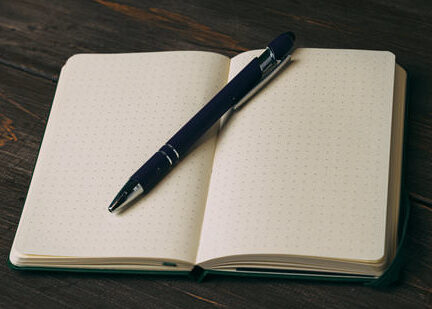【2024.10.27】vol.113 息が詰まるようなこの場所で
小学校の運動会があった土曜日。競技や演技を見ながら、我が子の成長を感じた。クラスメイトと和気あいあいと関わっている様子も嬉しい。なんかやんや運動会の雰囲気っていいものだと改めて思った。
*
運動会のあとに、片付けボランティアに参加。パパ友のつながりの場に誘ってもらって、少し驚いて、また一つ世界が広がりそうな気もしている。ゆるやかな人のつながりから、地域活動に根を張れれば、面倒さよりも、わくわくする感じがある。
*
プロ野球日本シリーズが始まり、ベイスターズに夢中になっている自分がいる。好きなチーム、好きなスポーツ、熱戦、そういったものが日常を熱くする。小学校の頃、昼休みに学校のテレビで日本シリーズを観たような記憶がふと蘇る。
*
自分用にバスケットボールを新しく購入したら、子どもの頃のワクワクした気分になった。それを持って、ミニバス練習に参加。始めは遠慮していたけれど、ボールを取り出して、自分でドリブルしたり、動いてみたら、楽しくて充実した時間になった。ためらわずに動いたその1歩で、息が詰まるこの世界とその時間を変えることができる。
*
小5の息子と初めてのBリーグ観戦。とどろきアリーナで、ビー・コルセアーズとブレイブサンダースの試合。今まで息子と行った野球やサッカー観戦はまったく空振りだったのに、今回、こんなに試合に夢中になっている息子の姿は初めてで、父として嬉しく思った。試合も延長に突入するほど白熱したナイスゲームだった。夜な夜な帰り道に豚骨ラーメンを一緒に食べた。こういう親子の時間が、思い出に変わり、いつかの記憶になるのだろう。いまを大切にしていきたいと思った。
*
仕事の悩み事や不安が自分の中で膨んで、家に帰っても付いてくる。ささいなことで自分が押しつぶされそうだ。膨らんだものは、ただの空っぽの泡みたいなもので、バブルのようにポンといつかはじける。このモヤモヤにもタイムリミットがあり、いつか消えてしまうことに自分でちゃんと気づいている。
*
息子が学校のプリントを持って帰るのを忘れて、妻がそれにプリプリと怒っていた。息子にもどこか抜けているところがあって、本人はあんまり危機感もなく、マイペースだ。それは短所のようで、動じないメンタルの強さでもあるようにも見える。親が子にイライラするのは、自分のためか、子どものためか、どっちだろうか。どっちもだろうけれど、めぐりめぐって、それは「子ども自身の課題」なのかもしれない。アドラーの「課題の分離」という考え方を思い出した。親としての役割は、子ども自身の自立を支えること。
*
ここしばらく仕事でモヤついていたことの1つ。必要物品の調査が、自分で調べて、ボスに相談して、ようやくやるべきことがクリアになってきて、前に進みはじめた。もやもやが一瞬で吹き飛んだ。「風向きはいきなり変わることもある」という言葉を改めて噛み締めた水曜日。重圧や重荷から解放されて、心は一気に軽くなった。
*
小説「息が詰まるようなこの場所で」を読了。タワマン文学と呼ばれるジャンルは初めて読んだ。40代で共働きで子育て世代である自分には、この物語がリアルに重なり、共感する部分もあった。他者と比較してしまうこと、忙しい毎日に追われていること、幸せってなんだっけとか、他に道はあったんじゃないかとか、ふと思う瞬間のこと。息が詰まる毎日でも、ふと息抜きする瞬間が訪れることもある。生きることは、息苦しくて、ままならなくて、それでも暮らしを繰り返して、時間は流れて、次のステップへと自動で流れている。男女の考え方の違いや、夫婦コミュニケーションの掛け違いもある。年収、資産、地位、学歴、そしてタワマンの居住階層・・・。結局、上を見ればキリがなく、下を見てもキリがないのだ。「人と比較しないこと」という価値観は、自分の中で大切にしていきたい。