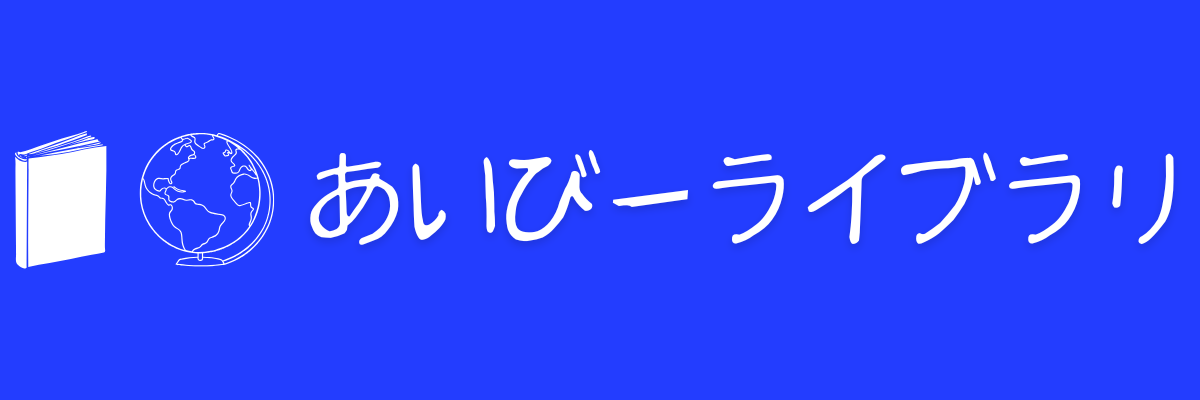2004年、ベトナムの旅

旅程:2004年3月7−13日
■旅のプロローグ
小林紀晴著「アジアン・ジャパニーズ」にこんな言葉があった。
『人は会うべき時に、会うべき場所で、会うべき人に会わなくてはならない』
『どんな出会いにだって、それぞれの意味が必ずある』
旅先で出会う人々。それは、日常の中にいる限り、出会うことのなかった人々だ。時間と場所がたまたま重なったとき、人は人と出会う。それは偶然かもしれないし、なにか不思議な力が働いた結果なのかもしれない。偶然であっても、それを必然や運命と名付けることもできる。「旅先での出会いは、やはり、ひとつの運命ではないか」と私は思っている。
中華航空が、ホーチミン・シティに着陸した。ムワっとするような東南アジア特有の熱気を肌で感じる。空港の出口の先には、観光客を待ちかまえているベトナム人たちが群がっている。そのオーラに圧倒されているとき、1人の日本人旅行者に話しかけられた。
「タクシー割り勘して、一緒に市内まで出ませんか?」
この人との出会いは、私の旅のスタイルに大きな影響を与えることになった。わずか数日、彼と共に旅をした短い時間の中で、本当に多くのことを学んだ。バックパッカーのスタイル、堪能な英語、現地の人々との自然なコミュニケーション。自分のペースを貫く姿に憧れを感じた。「あんな旅人になりたい」。今でもそう思っている。
■クチ・トンネル
ホーチミンの北西に位置するクチという町。ここは、ベトナム戦争のとき、南ベトナムの首都サイゴン(今はホーチミン)を攻撃するゲリラの拠点となっていた場所である。森の中に、地下迷宮ともいえる大トンネルがある。その「クチ・トンネル」を訪れるツアーに参加した。「シンカフェ」という現地代理店で申し込んだ格安ツアーだ。
ツアーバスが現地に到着すると、まず、案内ビデオを見た。ベトナム側の視点で制作されているため、反米ナショナリズムと、ベトナムの偉大さを感じる。展示スペースには、トンネルの模型があり、アリの巣のように地下深く広がっていることが分かる。狭い通路と所々にある居住空間は、地下三階まで掘り下げられ、随所に罠も仕掛けられている。ゲリラたちは、トンネルの内部でも戦うつもりだったらしい。
外に出て、森の中へ入っていく。森が持つ不気味さを何となく感じた。ふと自分を当時のアメリカ兵に置き換えてみる。視界の悪い森の中から、突然襲ってくるベトナム兵。ところどころに仕掛けられた罠…。当時のアメリカ兵は、「ベトコンはどこにも見えないが、どこにでもいる。」と言ったという。この森を歩いていると、その恐怖を実感する。
ある場所で立ち止まり、「ここにトンネルの入り口があります」とガイドが言った。地面の葉っぱを払いのけると、長方形の切れ目みたいな何かが現れた。それはフタのように外れて、アリの巣の穴のようになった。人ひとりが通れるくらいの本当に小さな入り口だ。
「誰か、入りたい人はいるかい?」ガイドがいう。すかさず私は一番に手を挙げて挑戦してみる。スポッと腰までは入ったが、肩を通すのはギリギリくらいだ。とても狭い。グラント(米国人のじいちゃん)に「入ってみたら?」と言うと、グラントは自分の大きな腹をタプタプしながら「ムリだよ!」と笑いながら言った。グラントのお腹は大きく、トンネルの入り口は小さい。
さらに森の奥へと進んでいく。いくつかのトラップが展示されている。仕組みは単純で原始的だが、とても効果的で実用的なものばかりだと感じた。最新兵器を備えたアメリカ軍に対抗するために、当時のベトナム人たちは最大限に知恵を振り絞ったのだろう。
射撃場に出た。ここでは当時の銃で実弾を撃つことができる。価格が10ドルで10発。初めての体験だ。撃ったときに右肩に感じる衝撃が強く、発砲音の大きさも凄まじい。どれもマトに当たらず、難しかった。
そして、いよいよトンネルの内部へ。中は暗くて狭く、蒸し返すような暑さを感じる。手と膝をつき、赤ん坊がハイハイするようなスタイルで、奥へと進んでいく。観光用に少し穴を拡張しているらしいが、それでも狭い。こんなところで戦っていたのかと戦時の状況を想像する。汗をダラダラかきながら、思った以上に長いトンネルを進んだ。ようやく出口から外に抜け出たとき、外の風が清々しくて気持ちがよかった。
■メコン川の夕暮れ
悠久なる大河メコン。その源流はチベット高原を発し、ラオス、ミャンマー、タイ、カンボジア、そしてベトナムなどさまざま国々を通過しながら、南シナ海へとつながる。その河口がメコンデルタだ。このメコンデルタ一帯には、ベトナム人たちの自然な暮らしがある。そこを訪れるツアーに参加した。同じく格安のシンカフェツアー。ホーチミンを朝出発し、バスは南へ向かう。
メコン川に到着。高速ボートに乗り換えて、水上からの風景を眺める。風に吹かれながら、ぬくぬくと育つマングローブの森は、どこまでも広がっている。水上に立てられた木造の家がいくつも並んでいて、そこにはリアルな暮らしがあった。この川は、彼らにとって母なる存在であり、生命そのものなのだ。そう思うと、この濁りに濁った緑色の川も、偉大なものに感じられる。
ランチのとき、スウェーデン人の家族と相席になった。若い人たちは普通に英語も話していたが、老夫婦は英語を話さないようだった。そこで教えてもらったばかりのスウェーデン語で話しかけてみたら、老夫婦は素敵な笑顔を見せてくれた。言葉の力ってすごい。
■カントーにて
ベトナムへ出発する前、友人から「忘れないよ!ヴェトナム」(田口ランディ著)という文庫本をもらって読んだ。喧騒とした大都市ホーチミンに嫌気がさしたランディさんは、田舎町であるカントーへ移動し、そこでベトナムの面白さを発見した。今回のメコンデルタ・ツアーでも、このカントーに泊まることになる。
川沿いの公園を散歩していると、「1アワー、2ダラー」と声を掛けられた。観光用ボートのお誘いだ。ランディさんも、このボートの悠久な時間がとても気に入ったらしく、毎日、夕暮れどきに乗っていたと本に書いてあった。
声をかけてきた若いお姉さんと、料金交渉を開始。コツは米ドルではなく、現地通貨である”ドン”で交渉することだ。2ドルだと約3万ドンなので、まずは1万ドンを目標にする。紙を取り出して、お互いに希望の料金を書きながら交渉していると、周囲にギャラリーがどんどん集まってくる。彼女は2万ドンを譲らなかったが、結局1万5000ドンで成立。日本人の感覚だと30円程度の違いだけれど、彼女にしてみればその差は大きいはずだ。それでも私が交渉をする理由は、できるだけ節約したいという気持ちよりも、こうやって人と関わり合うことを旅の中で楽しみたいからだと思う。
ボートが出航。川の支流に入っていくと、まるでジャングル・クルーズのようだ。狭い水路をゆくボートは、岸にガツガツとぶつかりながら、進んでいく。水路の脇に立ち並ぶ家々は、水上からは家の中が丸見えで、そこに暮らす人々の姿と生活があった。お金持ちになることが幸せなのかどうかはよく分からない。けれど、彼らと目が合い、手を振り、笑顔を見せてくれた姿を見ていると、こんな風に感じていられることが、幸せの一つのカタチなのかもしれないと思った。おおよそ1時間のクルーズで、ボート乗り場に戻る。最終的に、料金1万5000ドンに、チップとして5000ドンを上乗せして、ボート漕ぎのお姉さんに渡した。
■ホーチミン散策
ホーチミン市内を歩き回ろうと意気込んで早朝から街歩きを始めたが、1時間もかからず、その暑さにヘロヘロになり、旧大統領官邸「統一会堂」を見学したところで、散歩は諦めた。バイクタクシーを使うことにする。
バイクタクシーのドライバーたちが声をかけてきて、彼らが持っているサイン帳や写真アルバムを見せてくる。そこには、前に利用した日本人観光客が直筆で「このドライバーさんは安心ですよ」と日本語メッセージが書いてあったり、一緒にピースしている写真が載ってたりする。なるほど商売うまいな、と思った。ぼったくり不安を拭い去るには良い方法だ。効果的なマーケティングである。
今回は、カーさんというドライバーのバイクに乗せてもらうことにした。日本語を勉強中であるという。暑い日差しの下、つっ走るバイクで感じる風はとても気持ちがよかった。カーさんもなかなか良い人柄で、話していて面白かった。食堂でフォーや春巻きを食べたり、休憩中にコーラを飲んだりと、一緒に飲み食いするときは、費用を出してあげた。
「戦争証跡博物館」へと足を運んだ。戦争とは、ベトナム戦争のことだ。戦車や不発弾の他、枯葉剤による奇形児のホルモン漬けなど、強烈な印象の展示品の数々を見た。アメリカとは、戦争とは、科学とは、そして、今生きている自分の存在とは…。展示品を引き金に、自分の頭が難しいことを考え始める。博物館を出ると、頭の中でMr.Childrenの「タガタメ」という曲が何度も繰り返される。
『 子供らを被害者に 加害者にもせずに
この街で暮らすため まず何をすべきだろう 』
『 タガタメダ タガタメダ タガタメ タタカッタ? 』
■夜の散歩
夜の散歩をしていると、道端でベトナム人たちがよく話しかけてくる。「オンナ、スリーダラー」というのが一番多かった。××●や◇×●×などの日本語も聞こえてくる。こんなことでも、それをきっかけに現地の人たちと話ができるのが私は好きだ。こちらがノーとはっきり言えば、彼らも強引に連れていくつもりもなく、そこから「ところでベトナムはどうだ?」みたいな会話が自然と広がっていく。英語や日本語でカタコトな会話をして、肩を叩き合えば、互いに笑顔になってしまう。結局、人と人とのふれあいなのだ。そんな話をしていると、「あの女に付いていったら、男が出てきて大金を払わされるぞ」とかありがたい忠告ももらえる。真偽はともかく、善意や親切さを感じる。
「シクロ」とは自転車のタクシーだ。散歩中に、何度もすれ違う若い兄ちゃんがいて、自然と互いに顔を覚えてきた。年齢も近いようで、なんだか親近感を持った。「乗ってきなよー」と彼が言う。これも偶然の縁かと思えてきて、利用してみようと思った。ゲストハウスの名を告げて、「いくらだい?」と聞いてみる。すると彼は「タダでいいよ!」とこれまた危なげで怪しいことを言ってくる。「それは困る。ちゃんと値段を決めようぜ」と言うと、「up to you!(あなた次第だ!)」となかなか男気なことを言うので、これは面白いヤツだと思い、お願いすることにした。
フォム・グーラオ通りの宿まで帰る道。彼といろいろと話をしていたら、すぐに宿に到着した。相場もよく分からなかったので、10000ドン渡すことにした。彼はとても喜んでいたので、だいぶ多かったかもしれない。でも金額なんて結局、払いたい気持ち分だけ払えばいいのだとふと思った。そこにはボッタクリも何もない。そんなバランス感覚が少しずつ自分の中でうまく育っているような気がした。このベトナムの旅で、私は多くのことを学び、実践し、そして成長しているような実感があった。
■台湾へ寄り道
ベトナムからの帰路、飛行機の乗り継ぎが台北だったので、一泊することにした。「ストップ・オーバー」というもので、なんとなくお得な感じがする。寄り道の目的は「台湾の食」にありつくこと。一晩で夜市を歩き回り、食べるだけ食べて大満足。台北の街は、相変わらず何を食べても美味しくて、すぐにお腹がいっぱいになってしまう。台北の夜は最高だ。翌朝は、龍山寺へ立ち寄り、昼過ぎには、フライトの時刻となった。
■あとがき
「忘れないよ!ヴェトナム」という本は、自分にとって、この旅のバイブル的な存在であった。出発前に読み終えたとき、「これから行くベトナムという国は、必ずしもいいことばかりではない」という覚悟を持つことができた。旅行中も、動揺する場面に遭遇したとき、余裕をもって乗り越えることができたし、その全てを受け入れてベトナムという国を好きになった。この本を読んでいなかったら、もしかしたらベトナムとは「ケンカ別れ」してしまっていたかもしれない。
旅は常に偶然に偶然を重ねていく。タケさんとの出会いは自分にとってとても大きかった。別の国を旅しているときに、ふと彼のことを思い出すこともしばしある。クチトンネルのツアーで出会った、さんぺーさん&ハットリさんとはツアーの夜にサイゴンビールで乾杯したことも思い出深い。帰国後、さんぺーさんとは、新横浜で再会して酒を飲み交わす機会があった。日本での再会は嬉しい。人との交わりは、より一層、旅を豊かなものに変えてくれる。
以下、旅中に残した日記の文章をそのまま抜粋。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回の旅で得たもの。全くの無計画でも何とかなるということ。現地の人々との触れ合い方。旅人同士の交流。英語の必要さ。見慣れぬモノばかりで、自分の悩みとかがちっぽけに感じられて、また世界は広がった。いいこともたくさんあった。嫌なこともたくさんあった。でも旅は51パーセントのいい思い出があれば、勝ちなんだよな、きっと。テンパリながら、焦りながら、でもみんな笑うし、楽しいし、そういったことは人間みんな共通で。僕はまだまだで、これからで、でもまた1つ成長できた。知らないコトを知ったコト。それが大きな財産となって、次のステップへ。さぁ次の扉をノックしよう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー