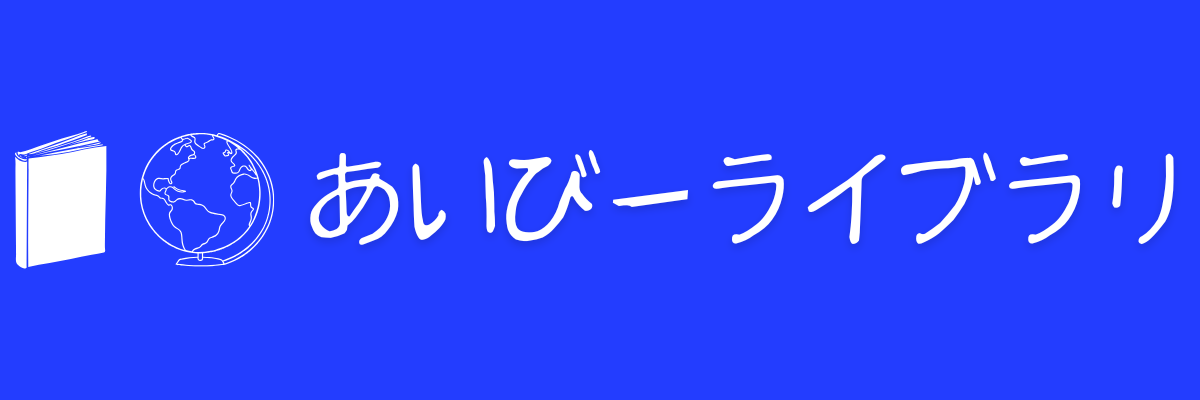2002年7月28日〜8月4日
ーーー進む道を見失っていた19歳。そんなときに出会った「スタディ・ツアー」が、自分にとって人生を見つめ直す転機となった――出会いがくれた、新しい視点と希望。
旅のはじまり
「自分の人生を変えた旅」というのは、このマレーシアの旅だけだ。
2002年6月。19歳の自分は、大学を中退し、人生の針路が全く見えなくなり、情緒不安定になっていた。
数ヶ月前、バイト先の先輩から、「1つのテーマがあるようなスタディ・ツアーに参加してみるといい」とアドバイスされたことを思い出した。インターネットで「国際交流」とか単語を検索していたら、横浜国際交流協会のホームページで、「体験マレーシア!植林&国際交流の旅」メンバー募集というツアーを見つけた。あの先輩が言っていたのは、こういうツアーだろうか。あまり深く考えず、直感的に応募してみた。
出発前には「事前研修」というものがあり、参加者の顔合わせや、ツアーの説明などがあった。参加者は全部で20人。高校生と大学生と社会人が混ざっていて、年齢層も15~28歳あたりと全体的に若い世代。男女比を見ると女性が多い。初対面ではあったが、すぐに打ち解けることができて、マレーシアに出発する前から飲みに行ったりなど親睦を深めた。
旅立つ
成田を発ったマレーシア航空は、マレーシアの首都クアラルンプールへ。そこから飛行機を乗り換えて、東に位置するボルネオ島へと向かう。今回の目的地は、ボルネオ島にある「サラワク州」だ。
機内で隣に座っていたツアーメンバーのひとりは、高校生。その高校に通う知人がいたので、もしかしてと聞いてみると、「きゃー!なんで知ってるんですか!?」と驚かれた。こちらも驚いた。私のバイト先の後輩と、彼女は友達だったらしい。世間は狭い。
クチン空港に到着したのは夜10時過ぎ。ツアーメンバーの1人の預け入れ荷物が出てこないというトラブルが発生。とりあえず見つかり次第、ホテルへ送ってもらうことになった。
遅い時間にも関わらず、サラワク州の関係者の方々は、我々を横断幕で出迎えてくれた。夜も遅いのでホテルへ向かう。いろいろ身辺整理し、ようやく眠りにつけたのが2時。翌朝(というか今日)は8時出発とのこと。
ホームステイ
プログラムの一発目は「ホームステイ」。マレーシア人の家に一泊させてもらい、生のマレーシア文化に触れる。私は、高校生の男子(以下、「相方」)と共に行動することになった。
ホストファミリーは中華系マレーシア人。ファミリーと言っても、30代ぐらいの男性2人で住んでいるという。兄弟と聞いたが、見た目は全く似ていない。集合場所に迎えに来てくれて、車で出発した。
クチンという街には猫博物館がある。そもそも「クチン」という言葉がマレー語で「猫」を意味するらしい。多くの家庭で猫が飼われていて、街中にも「猫の銅像」があるぐらいに、人々は猫が大好きなのである。猫を飼うと幸せになれる。器に水を張って猫を浸すと、恵みの雨が降る(猫には迷惑だな)。そんな迷信もあったりして、マレーシア社会と猫の関係についてはなかなか興味深い。
夜はフェスティバルがあるというので、出かけた。地元の人々が多く集まっていて、大音量で音楽が流れ、屋台もたくさん出ていた。
ホストファミリーの友人であるという女性がここで合流した。もともとクアラルンプールで仕事をしているのだが、ちょうど休みで帰ってきたらしい。どういう関係なのだろうと思っていたら、どうやら昔の奥さんとか何とか。
彼ら3人の中で、会話が弾み、英会話のスピードが上がってしまい、ほとんど聞き取れなくなってしまった。男4人のグループに、女性1人が入れば、まぁそうなるものだ。
フェスティバルが終わり、家に帰ると、私と相方は2階の部屋にこもってしまった。ベッドの上で、その日の出来事を振り返り、なんか、いつの間にか蚊帳の外に置かれてしまったな…と考えて、少し不快な後味も残ってしまった。一方で、自分にも積極的にコミュニケーションする姿勢が欠けていたのもよくなかったかなぁとも思った。
冷静になって考えてみれば、ホームステイというのは、私たちは「お客様」ではなく「家族の一員」なのだ。何もしなくてもファミリーたちが何かを与えてくれるわけではない。こちらからもアプローチしていかなくてはいけないのだ。そう考えると、新たな価値観の発見があって勉強になったなぁと今は思っている。
*
翌朝、ホストファミリーに起こされて、集合場所へと出発した。車で送ってもらい、日本食レストランに到着したのは、一番先だった。しばらくすると、各家庭に散らばっていたメンバーが徐々に戻ってきた。たった一晩だけだったけれど、なんか久しぶりな気がして嬉しかった。
両手いっぱいにお土産を抱えてきた人がいたり、ホストファミリーと抱き合って別れを惜しんでる人もいたり、それぞれホームスティを楽しんできたんだなぁと思った。
だいたいマレー系の家庭、中華系の家庭、イヴァン族の家庭と3種類ぐらいに分かれる。イヴァン族というのは、サラワクに住む原住民族で、かつては「首狩族」とも言われていたらしいが、現代では穏やかな人々である。家族がたくさんいる家、特に子供がいる家に行った人は特に楽しかったという感想が多かった。
その中でも、数少ない男性陣の最年長のF澤さんは、ホストファミリーも男性1人だったということである。男2人ではさすがに会話が続かなかったという感想をこぼしてくれた。
植林
ツアープログラムのメインの一つは「植林」である。熱帯雨林が豊富なマレーシアも、近年の伐採で、森林の減少が甚だしく進んでいるらしい。「地球上の熱帯林は、五秒毎に横浜スタジアム一つ分に相当する面積が減少している」と、手元の資料にはある。豊かな熱帯林を守るための森林保全プロジェクトを行っているのが、サラワク州の森林局というところだ。今回は、そこを訪問する。
この旅を語るうえで欠かせない人物が、マダム佐々木だ(仮名にしておく)。クチンに住む日本人で、現地でのさまざまな調整を担当している。マダム佐々木の経歴は、なかなか濃い。若い頃、日本で交際していたマレーシア人と結婚するために、周囲の反対を押し切って「かけおち」的に単身マレーシアへ渡る。今では旅行会社の社長、日本料理屋の社長、スナックのママという様々な顔を持つ。サラワク州の政府高官、実業界の主要人物にも広く顔が知られており、通称「サラワクの母」と呼ばれている。マダム佐々木が放つ空気は確かに「母」だ。
森林局を訪問した我々は、会議室に通された。そこで森林局の方々から「熱帯林の現状」や「森林保全プロジェクト」などの説明を英語で聞いた。英語が分からない我々のため、マダム佐々木が通訳をしてくれたおかげで、話の内容は大体理解することができた。
*
夕方からホテルに戻り、フリータイムになったので、ツアーメンバーの男3人でクチンの街を散歩してみた。デパートに入って涼み、そこで部屋飲み用のビールを買うことができた。街の中心には、広大な川が流れていて、その川岸が公園になっている。陽が暮れていく時間だ。オレンジ色の空と川面に映る夕陽のゆらゆらが、なんともいえない美しさを放っていた。
日記メモには、「夕飯はタイ風しゃぶしゃぶ。おいしかった」と書かれている。夕食の後、10人ほどで夜の公園に繰り出し、「ダンス」の練習。明日、現地の大学を訪問し、日本文化を紹介するというプログラムがあり、そこで我々はダンスを披露することになっているのだ。ラジカセで音楽を流しながら、踊っている日本人の集団。それは何だか宗教的な妖しさを放ち、通りかかるマレーシア人たちは「なんだ?なんだ?」と集まってきた。
練習も終わり、「飲みにいこうー!」という話になり、若者が集まってそうなバーへ。店内は、音楽がドガーン!ドガーン!と爆音で流れていて、隣に座っているメンバーの話も聞こえない。メンバー全員が同じことを感じたらしく、一杯飲んだだけで店を後にした。こんな苦い経験もあって旅はおもしろい。
*
翌日。バスが山奥に入ったとき、スコールが激しく降り注いだ。マレーシアの天気は変わりやすい。民族衣装を羽織った人々が出迎えてくれた。歓迎の酒を受け取り、それを一気に飲み干す。グワッとくるアルコールの強さ。
ステージでは、民族舞踊のショーが始まった。途中からメンバー数名もステージ上に呼ばれ、スローなテンポの舞いを見よう見まねで一緒にやっていた光景がなんとも面白かった。
そのあと、いよいよ植林体験へ。
苗木を埋めるために地面に穴を開けた箇所が20ほどあって、そこに苗木をどんどん埋めていく。2人1組での作業だが、このとき私のペアだった相手は、半年後、大学で再会し、奇しくも同じ部活の先輩後輩という間柄となる。人生の縁とは不思議なものだ。
植林自体は形式的なもので、雨が強くなってきたこともあってか、一つ一つ丁寧に思いを込めてやるというより、早く終わらせるためにパッパと作業を片付ける感じであった。それでも自分が植えたところには、自分のアルファベットの名前が書かれたプレートが立てられた。
「何年後かに、この場所に来れますかね?」と聞いてみたが、「難しいね」と地元の担当者が教えてくれた。ここは州政府の管轄の土地であり、個人で勝手に立ち入りできる場所ではない、ということらしかった。ここで植林作業に従事するマレーシアの人々は、男気あふれる工事現場のおっちゃん、みたいなカンジで、カメラを向けるととても気持ちのよい笑顔を見せてくれた。
国際交流
「青少年交流」というプログラム。日本の若者とマレーシアの若者が交流を楽しみ、相互理解を促進し、さらなる友好を深める。と書くと堅苦しいが、とりあえず私はこういうものが好きだ。
ここで我々メンバーは、年齢別で2グループに分かれる。高校生の「ヤングチーム」は現地の高校へ。私は大学生以上の「アダルトチーム」に入り、現地のサラワク大学へ。英語名のUniversity Malaysia Sarawakから、頭文字のUniとMaとSをつなげて、『ユニマス(Unimas)』と呼ばれる。
ユニマスに到着。キャンパスの敷地は広大で、建物は新しく、学生の数も多いらしい。今回はアザハ先生という方のゼミの学生たちと、交流することになっている。人数は15人ほどで、マレーシア人だけでなく、フランス人など多国籍なメンバー構成だ。
我々には「日本の文化を紹介する」というミッションがある。出発の前の研修で、①日本の昔話を紹介する、②日本の若者に流行しているJポップを紹介する、という2つの案に決まっていた。①は、日本人なら誰もが知っているポピュラーな昔話「桃太郎」を選んだ。その紙芝居を英語でやる。おまけに「ももたろさん」の曲も国境を越えて一緒に歌えばいい。②は、明るい!楽しい!みんなで踊れる!といったあたりから、V6の「WAになっておどろう」と決まった。こっちも国境を越えて一緒に踊ればいい。
まず、桃太郎の紙芝居。このナレーション担当は私が引き受けた。「Peach Boy」と英訳されたストーリーの原稿を、紙芝居をめくりながら読み上げていく。細かい話はほとんど割愛して、桃から生まれた⇒鬼退治に出かけた⇒犬に会って仲間にした・・・というような淡々としたアウトラインだけで鬼をやっつけた。そして、ローマ字で書かれた歌詞カードをみんなに配り、ももたろうの曲を紹介。先に日本人チームが歌い、そのあとでユニマスの学生たちも一緒に歌ってくれた。ユニマスの学生たちからは、「Peach Boyのお話は知らなかったよ!」「日本にこんな話があるんだね!」「教えてありがとう!」という言葉をもらった。
続いてJ-POP。我々メンバーの中に、小学校や幼稚園の先生がいたので、その経験とプロ魂を存分に発揮し、誰でも簡単にできる振り付けを作ってくれた。これが前述の「夜の公園で練習したダンス」である。教室で一つの輪になった我々は、日本人とユニマスの学生たちが混ざり合う形で、曲に合わせて踊った。これも好評だった。親しみやすいポップな曲調と簡単な振り付けのおかげで、大学生たちがみんな子供に戻ったような気分で楽しんでいた。私の隣りにいた、チャドルをかぶった女性も、素敵な笑顔を見せてくれた。人と人はきっと国境とか宗教とかを超えたところで、こうやって楽しさを共有できるのだ。
このあと、お茶とお菓子を食べながら交流と会話を楽しんだ。このときに仲良くなった同世代のホーくんというマレー人とはアドレスを交換し、帰国後、何度か手紙のやりとりするほどの仲良くなった。人懐っこくて、優秀な彼だから、今頃はきっとどこかで活躍しているのだろう、と想像している。
国立公園へ
バコ国立公園へ。その面積は約2700haと広大で、自然保護のため、許可なしで自由に公園内には入れないらしい。
クチン市内のホテルに滞在する我々は、1泊2日分の荷物を持ち、バコへと向かった。陸路では入ることはできず、水上ルートを使う。高速ボートに乗って海岸線を回り、キャンプ基地へと入るのだ。
ボート乗り場では、驚いたことに、先日のユニマスの大学生たちが待っていた。もともと一緒に行く予定ではなかったのだが、お互いの交流をもっと深めようということで、急にこのような形になったらしい。嬉しい話だ。
キャンプ基地に到着。我々の宿泊地もここになる。
貴重な自然が多く残るこの公園で、トレッキング。大自然の中を歩きながら出会う植物の数々に清清しい気分を感じた。
ロッジはビーチのすぐそばにある。水面はエメラルドグリーンに輝き、温泉みたいな生温かさの海が心地よい。360度が大自然に囲まれている。はるか遠くに小さな船影が見えた。ここだけは時間が止まっていて、カレンダーも必要ない。仲間たちと一緒に浜辺でビーチバレーを楽しんだ。
夜はバーベキュー。ユニマスの学生たちは、我々の「桃太郎」「V6」のお返しということで、歌とダンスを披露してくれた。これぞ異文化交流だ。
電気供給の関係で、午前0時になると、公園内の電気が一斉に消灯される。我々は砂浜に寝そべっていた。電灯が落ちると、満天の星空が広がった。静かな夜だった。波が静かに音を立てた。宇宙にたくさんの星があったことを知る。流れ星が輝いた。また輝いた。何度も、何度も。
日本で忙しい毎日を感じていた一方で、ここの時間は悠大にゆっくりとゆっくりと流れている。帰りたくないとは思っていないけれど、今はただこの緩やかな流れに包まれていたいと思った。
1時間ほど星空を眺めていたのち、ロッジに戻って眠りについた。
*
そして翌朝。6時過ぎに目が覚めたころ、部屋の相方が帰ってきた。浜辺でオールしていたらしい。高校生の彼はそのままベットで眠りについた。
私は、散歩に出かけた。朝早い時間だと、テングザルに会うことができる。
余談だが、我々は宿泊する注意点として「ロッジの窓には必ず鍵をかけてください」と説明されていた。ところが、F澤さんは、窓の鍵を空けたまま外出してしまったところ、サルの侵入を許してしまい、使い捨てコンタクトレンズを目茶目茶にされたらしい。F澤さんはこれ以来、メガネ生活を強いられることになった。
帰国のとき
バコ国立公園を出発するときがきた。「日本に帰ったら、打ち上げをやろう」と誰かが言って、連絡先を交換した。この旅も、少しずつ終わりに近づいてきている。
最後の夜、マレーシアに住んでいる日本人のH田さんが、ご自宅の夕食に招待してくれた。希望者のみということで9人ほどのメンバーで自宅へ向かった。
H田さんはマレーシア人の旦那さん&その家族と暮らしている。その家はとても広く、すばらしいご馳走をお腹いっぱい頂いた。マレーシア料理ながら、日本人にも食べやすかったのは、H田さんの料理の腕前だろう。H田さんは20代後半ぐらいでとっても美人だ。
H田さんは、実はツアーの最初からプログラムに同行していた(と、このとき聞かされた)。横浜出身の日本人がサラワクに住んでいるということで、事務局がお声がけし、このような形になったらしい。
そのおかけで、最後にふさわしい、とても素晴らしい特別な夜となった。明日で日本に帰る。そのことがまた、より一層、気持ちを感傷的なものにしているのかもしれない。
<旅のメモより抜粋>
「マレーシアで過ごす最後の夜。そうか、もうこんなに時間は流れていたんだ。でもきっと希望の火は消えやしないと願う」
*
出発のとき。クチン空港には、マダム佐々木さんはじめ、在住日本人の方々が見送りにきてくれた。待ち合いロビーでは、ツアーメンバー一人ひとりが、簡単に感想などをスピーチした。それを聞きながら、旅の終わりの感情がこみあげてくる。女性陣の多くは涙を流していた。何ともいえない寂しさが募ってくる。マダム佐々木さんとハグをして、別れを惜しんだ。
<旅のメモより抜粋>
「振り返れば、出逢って別れての人生。全ての道が交わり、また離れていく。参加して得たものは計り知れなくて、本当に”ありがとう”の気持ちでいっぱいである。」
【完】
あとがき
19歳のときのマレーシアでの経験は、人生の転換点となった。大学を中退していた自分は、そこからまた大学を再受験し、人生を再スタートすることになったからである。